

葬 式 死者をほうむる儀式。 「大辞林 第二版」   冠婚葬祭、成人式、入学式、卒業式、創立式、解散式…… 儀式は厳粛に執り行われるものである、儀式と呼ばれるものが厳粛でなければ、 <儀式>と呼ばれる所以もない、<一定の作法・形式にのっとって行われる集団的行事>であるそれは、 その集団の意思を結び合わせる<厳粛>を不可欠としているからである、 従って、<厳粛>に同意を持たない者の参加を許すことがすでに<厳粛>ではないことになる、 何故なら、<厳粛>とは、<おごそかで、心が引き締まるさま、きびしくゆるがせにできないさま>であるから。 語の意義については、今回も三省堂「大辞林 第二版」のお世話になっているが、 このように記述して始めよというのは、権田孫兵衛老人の提案によるものである……。 夫の遺骸を荼毘に付するために送り出す、葬式の朝を迎えた小夜子であった。 通夜は、ほとんど一睡もせず、線香の煙を絶やさないようにと愛惜の念を抱く男性へ尽くしたのであった、 いや、そればかりではなく、さらに、ふたりの男性へ抱く愛欲の念から尽くしたのであったが、 美しい未亡人の前には、さらなる男性が早朝の訪問者としてあった。 端正な若々しい顔立ちに、すらりとした身体付きを黒の礼服に包んだその男性は、 一度実家へ帰った義弟の健三がやって来たのだと小夜子に思わせたが、 話し始めれば、それが健三の双子の弟である健四であることがわかって、びっくりさせられた。 健四は、イタリアへ留学していて、どうしても葬式には参列が無理であるとされていたからだった。 「ぼくが義姉さんのために、式に参列しないわけがないじゃないですか。 義姉さんあってのぼくなのですから……」 そのように微笑みを浮かべながら語る、愛くるしい義弟だった。 ところで、双子の兄弟が兄弟であるというありようは、実際にあり得ることには違いないであろうが、 少なくとも、四人の兄弟の序列という位置関係をわかりやすくするために、 両親が健一、健二、健三、健四、と名付けたのは妙案であっただろう。 小夜子にとっても、四人を相手とすることであれば、 いくら、多義多様性が<縛って繋ぐ力による色の道>の真髄であると言っても、 相似の陰茎は、序列という位置関係なしには、ただ混乱を招くということになりかねないであろう。 もっとも、ポルノグラフィという観点からすれば、相似の陰茎であろうと、 結ばれるふたりがオーガズムへ到達できるということがありさえすれば、多義多様性もなんのそのであるが、 ここは、権田孫兵衛老人の厳粛な<民族の予定調和>のお話なのである。 「小夜子義姉さんは、ぼくにとって、なくてはならない女性なのです。 一年前のイタリア留学へ旅立つ、ちょうど一週間前にあったこと…… ぼくには、決して忘れられないことです……」 玄関口での会話であろうとお構いなしに、気負い込んで語り始める相手から、 <決して忘れられないこと>と言われて、小夜子は、思わず、美しい顔立ちの両頬を赤らめるのだった。 その羞恥を隠すように、彼女は、とにかく上がってくださいと招き入れたが、 会えることを切望していた相手を間近にした喜びは、青年の思いを飛翔させて独り語らせるのだった。 「あの日、健一兄さんは出張で出かけていて不在でした…… ぼくは、それを知っていたから、お昼に合わせて訪ねていったのでした。 健一兄さんのいないときに、小夜子義姉さんの手料理でお昼をご馳走になれる、こんな幸せはありません。 何故なら、健一兄さんは、五人いる兄弟姉妹のなかで、最もぼくを毛嫌いしていたからです。 ぼくがれっきとした男性でありながら、女性と見間違われるほどの美しい顔立ちをして、 優美な曲線さえあらわす綺麗な身体付きをしていたからです、しかも、その上に、 兄弟姉妹のなかで、小夜子義姉さんから、最も優しく思いを掛けられていた存在でもあったからです。 小夜子義姉さんは、ぼくのなよなよしている女性的なところをいつもかばってくれるようにしてくれました。 ぼくは、そのような優しい心遣いの小夜子さんを実際にふたりいる姉以上に、 本当の姉だと思えるほど、好きでした。 ですから、あの白昼、小夜子義姉さんのあのような姿を見せられたぼくの衝撃は、どれほどだったでしょう! ぼくは、家の玄関チャイムを鳴らしました。 しかし、いくら鳴らし続けても、義姉さんは、姿をあらわしてくれませんでした。 不審を感じたぼくは、玄関扉のノブをまわしたのです、すると、錠は下りていなかったのでした。 無用心であると思いながら、ぼくは、家のなかへ入りました、そして、義姉さん、と声を掛けたのです。 しかし、返事がありません、不審は不安へ、どんどん変わっていくものとなりました。 ぼくは、義姉さん、義姉さん、と声を掛けながら、玄関から奥へと上がり込みました。 そして、日本間の造りになっている部屋で義姉さんを見たのです。 信じられないことでした! 義姉さんが一糸も着けない生まれたままの優美な裸身を晒しているのです! それだけでも、とても信じられないことでしたが、 その乳白色に輝く柔肌には、厳しい縄が雁字搦めに掛けられていたのです! 小夜子義姉さんは、畳の上へ、身体を真っ直ぐに横臥させられるようにして転がされ、 優美な姿態は、両手を後ろ手にして縛られ、 綺麗なふたつの乳房は、突き出させられるような胸縄を上下から施されていました。 さらに、ほっそりとした首筋から縦へ掛けられた縄が胸縄へ絡められて腰まで下ろされ、 艶めかしい曲線を描く腰付きのくびれがいっそう際立つように、巻き付けられ締め上げられていたのです。 ああ、でも、それだけではなかったのです、その上に…… 腰縄は、愛らしいお臍のあたりから股間へ向かって縦へ下ろされ、、非情にも、もぐらされているのでした…… 漆黒の夢幻を思わせるようなふっくらとした艶やかな靄のなかへ、 女性をあらわす割れめへ深く埋没させられているのがはっきりと見て取れるほど、 それは、あからさまであったのでした。 見るも淫猥な羞恥を耐えるように、雪白の柔和な太腿を貞潔にぴったりと閉じ合わせていることが、 股間の麻縄をいっそう淫乱で邪悪なものと映らせているのでした。 もちろん、ぼくは、女性が全裸を縄で縛られた画像を見たことがなかったわけではありません。 縄による女体の全裸緊縛、二十歳以上の成人指定…… むしろ、そのような画像を一度でも見たことのない十九歳を探す方が稀有と言えることではないのでしょうか。 それは、男性の淫情を掻き立て煽り立てるために、これでもかという卑猥をあらわすものとして、 世界に数多ある猥褻表現のなかでも、まさに、比類のない日本独自のお家芸としてあることのようです。 縄による女体緊縛については一言ある、一家言ある、 縄掛けるありようとはこうだ、ああだ、そのようだ、と多種多様に緊縛の美学なるものが示されて、 書籍やビデオやゲームやインターネットで明らかにされていることです。 ぼくも、そのくらいのことは知っていましたから、小夜子義姉さんの全裸緊縛姿を見せられたとき、 強い衝撃と共に、淫猥、卑猥、淫情、劣情、猥褻の思いが駆けめぐり、激しく動揺させられたのでした。 淫乱であるなどとは到底思っていない小夜子義姉さんに対する、ぼくの真面目な思慕などまるでよそに、 ぼくの淫乱な陰茎は、しっかりと淫情をあらわして、もたげさせられてしまっていたのでした。 そして、見つめ続ければ見つめ続けるほど、眼の前にさせられている女性の全裸姿ほど、 妖美で、妖艶で、艶麗であると思えるものを見たことがないと感じさせられていたのですから、 何という思慮と官能の倒錯であったことでしょう! いや、生まれたままの全裸を縄で緊縛された姿態にある、その女性の顔立ちを見つめるに及んでは、 うっとりと恍惚となった表情を浮かべている法悦的なその美しさは、 いままでの小夜子さんに見たことは決してなかったことだと思い至らせられるのと同時に、 このひとこそは、この世に、ただひとりの美しい女性だと思わせたのでした! 何という思慮と官能の転倒であったことでしょう! ぼくは、もう、胸が痛いくらいに激しく心臓が高鳴り、顔が火照り上がり、ぼおっとなってしまっていて、 ただ、取り憑かれた者のように、立ち尽くして、凝視しているばかりでした。 綺麗な赤い唇を半開きにして、深い快感に漂わされているような薄目がちのまなざしを惑わせて、 小夜子さんは、ぼくの存在になど、まったく気づいていないという様子でしたが、 日本間にもうひとりいた人物には、わかっていたことだったのです。 その人物は、突然、ぼくの前へはだかったのでした。 はだかったと言っても、小柄な老人でありましたから、大した図体のものではありません。 しかし、その老人の容姿をひと目見たとき、ぼくは、全身を貫く強い戦慄を感じさせられたのでした。 まるで、鋭利な刃物を直接心臓へ突き付けられた思いでした。 禿げ上がった真っ白な頭髪に歯のないくぼんだ口もと、どぎつい目つきや鋭い鷲鼻、 皺だらけの小柄で痩せ細った身体が薄っぺらな着物に包まれて、険しい老いだけがあらわとされている姿! 喩えて言うならば、月岡芳年という画家が『奥州安達ケ原ひとつ家の図』という錦絵で、 天井から逆さ吊りにさせた半裸の妊婦を切り裂くために包丁を研いでいる鬼婆を描いた、 それとまさに瓜ふたつ、双子のようにそっくりの老人であったのでした! 「おまえさん、この女に何か用でもあるのかい? いま、取り込んでいる最中だから、出直してきた方がいいんじゃないか。 この女は、<夢の告知>を受けている真っ最中なんだよ。 わしがこの女の夢のなかにあらわれて、 <縛って繋ぐ力による色の道>を身を持って教示しているということだ。 おまえさんは、その女の夢のなかへあらわれてしまったというわけだ。 恐らく、おまえさん、この女へ対する思慕が相当に強いのだろう、そうでなければ、あり得ないことだ。 だが、この女は、いま、恋愛に身を寄せている場合じゃない、 もっと火急な性的官能にみずからを立ち向かわせているところだ。 さあ、わけがわかったら、さっさと立ち去りな!」 背筋まで凍らされるような気味の悪さを帯びたしわがれ声は、そのように言うのでした。 ぼくは、何のことを言っているのか、さっぱりわかりませんでした。 ただ、ぼくが小夜子さんを慕っていること、眼の前に、小夜子さんが緊縛の裸身としてあることは、 事実であったことなのです! 「で、でも……義姉さんは…… 小夜子義姉さんは、ど、どうして、このような、このような酷い目に…… このようなこと、やめてください! 小夜子さんが可哀想です!」 ぼくは、思わず、言ってしまったのでした。 すると、老人は、にらみつける恐ろしいまなざしで、怒鳴り返してきたのでした。 「若造のくせに、わかった風な口をきくんじゃねえ! おまえに何がわかっていると言うんだ、おまえは、いま、そこで見惚れていたんじゃねえのか! 何が可哀想だ、何が酷い目だ! 見惚れて、おちんちんをおっ立たせていて、何がやめにしてくださいだ! 立たせられたおちんちんなら、 そのように煽り立てられた相手と行くところまで行かなきゃならないことだろうが! それが、折り合いを付ける、辻褄を合わせる、収拾を付ける、整合性を成す、ということじゃねえのか! 画像を見たり、文字を読んだり、悩ましい声音を聞いたり、空想したりして、そうなったおちんちんだって、 煽り立てられた対象とひとつに結ばれるように、みずから独りでしごいて行き着くことをするんじゃねえのか! おまえの言っていることは、まるで辻褄が合っていねえじゃねえか! 整合性のない映画や小説や音楽や夢想といったものを、だれが納得すると言うんだ! ばかやろう! わしは、言っただろう、おまえは、この女の夢のなかにあらわれてしまったのだ、 わしは、<夢の告知>が終われば、この女の思いのなかから、すっかり消えてしまう、 残るのは、女の肉体に刻み付けられた縄の緊縛の感触だけだ! だが、おまえは、この女がその存在を知れば、心象として、いつまでも残り続けてしまうのだぞ! それは、<色の道>としてある情愛や恋愛を、おまえが激しく持っているからだ! 人間には、情愛や恋愛というものがある、男と女の愛、男と男の愛、女と女の愛、というものだ。 このような三様の情愛や恋愛が老若を問わずに人間に可能であるからこそ、 情愛や恋愛は一義の意味しかあらわさないという不確かさを超えてあるのだ! 真の確かさというものは、多義多様性においてこそ、あるということだ! それを男と女の恋愛のありようだけが唯一、絶対、永遠のように吹聴されているとしたら、 それが愛の本質をあらわしているというよりは、 その結合からもたらされる種族保存と維持が明らかにされているに過ぎないことだ! 人工授精が堕胎と同じくらいに日常茶飯事となった時代には、 三様の情愛と恋愛は、すべて等しい価値と見なされることだ! 愛の本質とはそいうことだ! 愛は、多種・多義・多様の情愛と恋愛として存在し続けるからこそ、 <色>は<色>として、色あい・明るさ・あざやかさの属性によって光り輝くものとなるのだ! <色>の尊厳、光輝、崇高ということだ! そのようなことも、わからないくせに! 余計な口出しをするな! ばかものが!」 ぼくは、もう、その八十歳は優に過ぎていると思える老人の迫力に圧倒されて、唖然となったままでしたが、 それ以上に、老人の語っている事柄がまったく理解のできないものとしてあったのです、 まるで、頭のもうろくした者がたわごとか荒唐無稽を喋っているようにしか、聞こえなかったのです。 そして、突然、老人の気味の悪いにらみつけるようなまなざしは、 ぼくの上から下までを舐めるような執拗さで這うようなことをしていたのでした。 「ほおう、おまえさん! まるで、女のような美しい顔立ちをしているな! 着ている衣服の線からしても、身体付きも、女のように優美な線をしているんじゃないのか! 捜してもそうは見つからないとされている、逸品の<陽間>というものじゃないのか、おまえさんは! よし、着ているものをすべて脱いで、そこへ裸になってみろ!」 言われたことの法外に、ぼくは、もう、びっくりしてしまって、唇をわなわなと震わせているばかりでした。 「ほおう、狼狽した様子も、随分と女っぽい感じを漂わせるじゃないか、可愛らしい! わしは、美しく愛らしい女性が大好きだ! さあ、さっさと生まれたままの全裸の姿をさらせ! 実際を見せてみろ! 早くしろ! 生い先のない老人は気が短いんだ!」 ぼくは、いったい何を言われているのか、頭は混乱するばかりでした。 いつまでも立ち尽くしたままでいることに、老人は、ついに業を煮やしたようにぼくの方へにじり寄ると、 スーツの上着を脱がせようとし始めたのです。 「いやです! どうして、ぼくが裸になんかならなければならないのです! やめてください! さわらないでください!」 ぼくは、両腕を掻き抱いて、あらがいました。 老人は、それでも、執拗に皺だらけの骨と皮のささくれだった手を伸ばして、諦めないのでした。 ぼくは、いやっ、いやっ、と悲鳴を上げていました。 そのときでした。 「健四さん、お願いです、逆らわないで、お願いです…… その方は導師様なのです……」 畳の上へ、縄で緊縛された全裸を横臥させていた小夜子さんが美しい声音で呼びかけたのでした。 ぼくは、はっとなり、妖しく美しい相手を見つめていました。 小夜子さんは、官能にほだされた上気した顔立ちで、 しかし、綺麗な澄んだ瞳を大きく見開いて、見つめ返していました。 ぼくには、どうしたらよいことなのか、もう、わからなくなってくるばかりでした。 なよなよしているぼくのそういう女性的なところを、小夜子さんは、いつもかばってくれるようにしてくれました。 ぼくは、その優しい心遣いの小夜子さんを本当の姉だと思うほど、好きでした。 小夜子さんの言うことであれば、何でも聞けることだと思っていました。 けれど、いまあることは! この場で全裸になるなどということは! 「一糸もまとわない、生まれたままの全裸の姿になるということは、そんなに難しいことではないだろう! おまえさんがいま眼の前にしている女だって、優美な姿態を見事にさらけ出しているじゃないか! 優美な姿態を持っている者は、ことさらに、その優美さをひとから見られることを望んでいるものだ! 人前へさらけ出したくないと口では言っても、 さらけ出すことが自己満足を超えた優越を生ませるほどに欲望させるのだ! ただ、それを行わせるには、<もっともらしい理由>が必要とされるだけだ! 全裸は、特別な能力などなくても、誰でも容易になれることでは、老若男女に差異はない! これほど平等の価値を純粋にあらわしている事柄は、人間の平等の概念では他にない! 人間の全裸というありようは、 この地球上に生息する生き物すべての全裸との平等を明白にしていることだからだ! だから、人前へ全裸をさらけ出すだけのことでは、他の生き物と同等であることをあらわしているに過ぎない! 人間としての能のないことをあからさまにさせているだけだ! 能ある鷹は爪を隠す、同じように、能ある人間は全裸を隠さなければならないということだ! つまり、全裸をあらわしていながらも、隠している全裸でなければならないということだ! これは矛盾している事柄のようだが、結び合わせる理由というものがそれを可能とさせるのだ! それが<もっともらしい理由>ということだ! 全裸を全裸自体であらわすことをさせない理由ということだ! 人間は、全裸でありながら、絶対に全裸には成り得ないということだ! その<もっともらしい理由>とは、如何なるものであるか。 それは、<人間であるが故に生じる>とされている事柄のいっさいだ! 人間が他の生き物との差異としてあらわそうとしている事柄のすべてだ! いま、おまえさんが目の当たりにしている縄による全裸の緊縛姿ということだって、 その<もっともらしい理由>があるということだ! 女が生まれたままの全裸を縄で縛り上げられる、どうして、このようなことがあるのか。 女に対する虐待、すなわち、人間に備わる加虐・被虐の性的属性が行わせる、 <人間であるが故に生じる>人間であることの行為! 女が非人間的に取り扱われるからこそあからさまとなる人間らしさの行為! この地球上に生息する他の生き物において、 自然から生まれた植物繊維を撚り合わせた縄で対象の雌を緊縛する存在はあり得ないということでは、 人間としての唯一、絶対、永遠が明白に露呈されているという行為! すなわち、人間にとっての不変の性的属性があるという<もっともらしい理由>によるものだ! だが、それだけでは、説明のつかないことがある、おまえさんが、この女の全裸緊縛姿を見つめて、 妖美で、妖艶で、艶麗であると思えるものを見たことがないと感じさせられた、 思慮と官能の倒錯が説明されていることにはなっていない! 加虐と被虐という二項対立の弁証法を<人間であるが故に生じる>という総合として見る限りでは、 美意識は、それらを舌触りよく賞味させるオブラートの曖昧さでしかないのだ! 言ったように、<人間は全裸でありながら絶対に全裸には成り得ない>ということがあるのだ! 縄による緊縛は、それを明らかとさせている表象だ! 縄による全裸の女体緊縛がわれわれに教える人間の存在認識だ!」 気味の悪い老人は、老人の自己主張とも言えるような頑迷な調子で、 まるで、ぼくの存在など彼方にあるような様子で、喋り続けているのでした。 語られていることの法外は、ぼくをただ茫然とさせていくばかりことだったのです。 「<人間は全裸でありながら絶対に全裸には成り得ない>ということをあらわす縄ということだ! 縄を身にまとわされてこそ、始めて至ることの可能な想像力があるということだ! <人間の抱く想像力こそが人間本来のものとしての神であるというヴィジョンを実現すること>、 これがわれわれの<民族の予定調和>としてあるわけは、 生まれたままの全裸へ掛けられる縄が全裸でないことを顕現している想像力であるからだ! わしは、それをおまえさんに認識させてやろうというのだ! さあ、さっさと裸になれ!」 老人は、ぼくの反応も待たずに、畳の上に置かれてあった麻縄の束を取りに行っているのでした。 ぼくは、もう、不可解が狼狽と不安と恐怖を張り付かせて、身体をすくませているだけでした。 「何だ、まだ、裸にならないのか! 女の腐ったみたいな優柔不断のぐずぐずしている奴だ! では、おまえさんが納得するような<もっともらしい理由>を語り聞かせてやろう! おまえさんは、逸品の<陽間>かもしれないということだ! おまえさんは、ひとに見てもらわなくてはならない格別の姿態を持っているかもしれないということだ! <縛って繋ぐ力による色の道>において、<陽間>と呼ばれる存在がある、 れっきとした男性でありながら、女性の優美さとまったく変わらない姿態を持っている者のことだ、 但し、男性である以上、おちんちんが付いていて、豊満な乳房というものがない、 そして、最も肝腎なことは、その抱いている思いというものが女性そのものであるということだ! そのような<陽間>は、世の中を捜してもそうは見つからないとされている。 もし、おまえさんがそれであれば、おまえさんが全裸をあからさまにさせないというのは、 まったく辻褄の合わない話だ、何故なら、おまえさん自身こそ、 そのみずからの優美さを誰よりも賞賛している者はいないからだ! ただ、その外見の矛盾と心の相反は、世間からは異様だという取り扱い方をされ、 おまえさん自身がみずからを異常だという疑問を持っていることであれば、ただの苦悩のお話に終わる、 <民族の予定調和>においては、ただの苦悩のお話に終わるようなものなどない! 人間にある想像力は、その者を生かすために用いられてこそ、神のありようとして繋がるものだからだ! <民族の予定調和>の表象となる女性は、 生まれたままの全裸の姿を自然の植物繊維から生まれた縄で緊縛されれば、 年齢に関わらず、<表象>としての女性となることができる、 そして、<信奉者>としての男性と縄によって結ばれながら、 <縛って繋ぐ力による色の道>を歩み続けることが求められる、 これは、根本的なありようだ、ほとんどの者がそのようにある、 そのなかで、<陽間>と呼ばれる者は、女性にのみならず、男性にも結ばれる格別の存在としてあるのだ! さあ、おまえさんが格別の存在であるかどうか、明らかにしてみろ!」 老人の言葉は、まるで、ぼくを見抜いているという説得力があったのでした。 れっきとした男性でありながら、女性の優美さとまったく変わらない姿態を持っていたぼくは、 覆い隠しているものさえ剥ぎ取れば、 老人の語る<陽間>と呼ばれるものをあらわすことは間違いなかったのです。 老人のにらみつける恐ろしいまなざしは、もはや、逃れられないものをぼくに感じさせていました。 ぼくは、思わず、畳へ横臥している小夜子さんを一瞥していました、そして…… 美しい女性のそのまなざしが憧憬と慈愛を滲ませたものとして感じられたことは、ぼくを決心させたのでした。 震える指先は、身に着けていたスーツのボタンを外し始めていました。 みずからの全裸を小夜子さんの前であからさまにさせることは、たまらなく恥ずかしいことでした。 男性が男性として誇れるような男性のあらわされる立派な身体付きをしているわけではないのです。 女性が女性らしさをあらわす艶めかしい曲線に包まれた身体付きに、 ふくらみのまったくない乳房と余りにも可愛らしい陰茎が皮を被って付いているというものであったのです、 柔肌も雪白に、股間の恥毛を除いては、脱毛していると見なされるくらいに、なめらかさのあるものでした。 ぼくは、そのありように苦悩して、女性として生まれ変わることを真剣に考えたことがあったのでした、 それほどに、目を見張らせるほどしなやかで優美と言える裸身であったのです。 全裸になったぼくの姿態をまざまざと見た老人は、ほおう、見立ての通りだ、と溜め息をついていました、 顔付きをにんまりとさせたのかもしれませんが、険しい老いの表情は無表情にしか見えないものでした。 それに比べて、横目で見た小夜子さんの顔立ちでした、大きな美しい瞳をさらに大きく見開いて、 驚愕と当惑と憧憬の表情を漂わせながら、ぼくをしっかりと見つめていたのでした。 たまらなく恥ずかしいぼくの思いをよそに、 ぼくの小学生ほどの可愛らしい陰茎は、恥ずかし気もなく、しっかりともたげてしまっていたのでした。 ああ、何処かへ消えてなくなりたいほど、恥ずかしかった! 「両手で隠すんじゃない! 両手は背中の方へまわすんだ!」 ぼくは、思わず、胸と股間を覆い隠してしまっていたのでしたが、 恐ろしい老人は、近づくなり、ほっそりとしたその両腕を背後へと強引にねじ曲げたのです。 ああっ、いやっ、と叫ぶぼくの声音などお構いなしに、 老人は、八十余歳とは到底思えないような腕力で、簡単に両手首を背中へまわさせたのでした。 そして、生き物を操る手際良さという素早さで、重ね合わさせたぼくの華奢な両手首を縛り上げると、 縄尻を身体の前の方へ持っていって胸の上部へ二度ほど巻き付け、背中でそれを縄留めすると、 すぐさま、二本目の縄を背中で結んで、今度は胸の下部へ二度ほど巻き付けて、 背後から腋の下へもぐりこませては、左右から胸縄をがっちりと固定させていくのでした。 縄で縛られることなど、生まれて初めての経験でした、ましてや、全裸の姿をです! 両手を不自由にされ、思ったような身動きを許されないという境遇がこれほどまでに、 意思を狼狽と不安と恐怖へさ迷わせるものだとは思ってもみませんでした。 しかも、生まれたままの全裸であることが、それだけでも恥ずかしいという思いにあったのに、 全裸を縛られたことは、顔立ちを火照り上がらせるほどの激しい羞恥を感じさせるものがあったのです。 さらに、その高ぶらされる羞恥は、もたげていた陰茎を恥も外聞もなく反り上がらせていたのです。 ああっ、いやっ、ああ、いやです、と切ない声音をもらしながら、 羞恥と狼狽と官能に舞い上げられたように、ぼくは、緊縛の裸身を身悶えせずにはいられないのでした。 「仕草が艶めかしく女っぽいところは、なかなかのものだ! 全裸を縄で縛られたことで、抱いている思いが女性そのものであるということに目覚めたというわけだな! だが、それが本当の自分だなどと思うな、本当の自分など、存在しない! 自分というのは<自ら分かつ>と書くように、多義多様にあってこそ、自分というものがあり、 その種々の様相を折々の居心地のよさとして選んでいるものが自分であるということに過ぎない! おまえさんの居心地のよい自分というものが女性そのものであるということに過ぎないのだ! 自分というのは<自ら分かつ>ことの総体であって、 <本当の自分捜し>というようなことが物語やゲームのようなものにしかならないのは、 その総体は、分かたれた自分というものひとつによっては、把握できないからだ! 自分というものは、ひとつではあり得ないからだ! ひとつではあり得ないものをひとつとして求める、ここに苦悩の生じないわけがない! まさに、文学的に言えば、成し遂げられない超克をあえて苦悩するという、美しい苦悩というところだ! 美しい苦悩もいいことだが、やはり、美しい見栄えということも大切だ! やはり、どのように見ても、おまえさんの目を見張らせるほどしなやかで優美と言える裸身には、 その可愛らしい反り上がりは、めざわりということになるわけだ! <縛って繋ぐ力による色の道>においては、どのように美しい男性であろうと、 男性に掛ける縄は不浄とされているのだ、その不浄を浄化するためには、 信奉者の流儀に従って縄を掛けられた男性が縄で縛り上げられた女性と結ばれることでしかあり得ないが、 <陽間>とされる者には、その女性をあらわす特有の縄掛けがあるのだ、さあ、両脚を開け!」 老人は、そう言うと、一本の麻縄を手に取り、ふた筋にした頭に小さな環をこしらえ始めたのです。 それから、ぼくの陰茎をおもむろに掴むと、その環を根元へ掛けたのです。 縄は股間を通されて尻の方へ持っていかれました。 「ああっ、いやっ、いやっ、そんなことは! いやっ! いやっ! いやっ! やめてください! やめてください!」 ぼくは、行われていくことがわかって、もう半分泣き声になりながら、 緊縛の裸身をくの字に折り曲げて、両方の太腿をぴったりと閉ざして、懸命なって抵抗しました。 だが、老人は、くの字になって、むしろ、突き出すような具合になった優美な尻を待っていたのです。 老人のささくれだった骨と皮と皺の指が菊門を優しく強くなぞり始めていたのでした。 そのおぞましい感触はびくっとさせられるほどのものでしたが、 異様な快感と言うようなものを双方の太腿の付け根から走らせて、 閉じ合わせていた両脚の力を脆弱なものとさせていったのでした。 それから、指は、徐々に、奥へ奥へと沈み込まされていったのです。 「ああっ、痛い! やめてっ! やめてっ!」 湿り気をまるで帯びていない箇所は、裂かれるような具合に押し広げられて、ぼくは、悲鳴を上げていました。 しかし、老人の指は、容赦はなく、指の根元まで沈められていき、淫靡にうごめかされたのです。 「可愛い反応を示すな、いいぞ…… 安心しろ、もうすぐ、気持ちのいい思いにまで導いてやる!」 激しくうごめかされる老人の指は、膨れ上がったような感触で、灼熱の淫乱さをあらわしたのでした。 ぼくは、下半身が一気に脱力させられるような強烈な疼きを感じさせられ、 立っていることもままならない状態になっていました。 双方の太腿から付け根へ這い上がる快感が陰茎をこれでもかと反り上がらせて、 ぼくは、老人のうごめかされる指に合わせて、優美な尻を淫らに振らされているのでした。 そして、こらえる思いなどよそに、両太腿から背筋まで貫かれるような快感の疼痛を意識させられて、 反り上がっていた陰茎から放出を始めてしまったのです。 抑えることなどまったくできずに、押し出されるようにいってしまったのでした。 それは、恥ずかしくも、小夜子さんの横臥させられているあたりまで、白濁とした液を飛び散らせたのでした。 ぼくは、もう、愕然となってしまって、畳の上にへたり込まずにはいられませんでした。 だが、陰茎へ掛けられて股間へ通されていた縄を取っていた老人は、それを許しませんでした。 抜き取られた指の代わりに、縄は、優美な尻の亀裂の間から引っ張り上げられていたのです。 硬直の失われたぼくの可愛らしい陰茎は、強引に股間へもぐり込まされていったのです。 「ああっあ〜ん」 ぼくは、切ない泣き声を上げるだけで、 そのようなことをする老人へ非難を吐き捨てる言葉はおろか、見やることさえもできませんでした。 ぼくを意のままにオーガズムへと導いた、忌まわしくも、おぞましくも、恐ろしい老人だったのです! <導師様>と小夜子さんが呼んだ、その意義通りにぼくを導いた老人だったのです! ああ、ぼくは、もう、死にたいくらいの恥辱にありました。 破廉恥にも、射精を向けてしまった小夜子さんの方へまなざしを寄せるなんて、到底できないことでした! ぼくは、精一杯首をうなだれて、必死に現実を見まいと、両眼と唇を閉じるほかなかったのでした。 恥ずかしさと哀しさと恐ろしさが快感の余韻とまぜこぜとなって、めがしらが自然と膨らんでくるのでした。 だが、何という非情な老人であったのでしょう、ぼくに内省の余裕など少しも与えることなく、 ぼくのしなやかな両脚を無理やり開かせると、最初の目的を果たそうと作業を続けているのでした。 ぼくは、もう、成されるがままでした、閉じた両まぶたからあふれ出した涙の流れ落ちるままでした。 自棄気味になっていて、まるでひとごとのように、すねた思いに縮こまってしまっていたのです。 そのときでした。 横臥させられている緊縛の裸身をうごめかせて、小夜子さんがぼくの注意を惹き付けたのでした。 「健四さん……本当に、ごめんなさい…… 私のために、このようなことになってしまって…… 私がみずから選んだ民族の女としての<色の道>へ、あなたを巻き込んでしまって…… でも、あなたが<陽間>であったこと……私には、驚きであると共に喜びでした…… あなたが世の中を捜してもそうは見つからないとされている男性であることは、 私にとって、大変に光栄であると感じさせられたことだからです…… 何故なら……何故なら……私は、あなたをずっと好ましい方だと感じていたからです!」 小夜子さんの澄んだ大きな瞳には、きらきらとした涙があふれているのでした。 それにしても、何という感動的な言葉が聞けたことでしょうか。 小夜子義姉さんは、ぼくを好ましい方だと感じてくれていたのです! それに対して、ぼくは、何ということをしてしまったのでしょう! 「いや、義姉さん……いや、小夜子さん、謝らなければいけないのは、ぼくの方です! 恥ずかしく失礼なものを飛ばしてしまって!」 ぼくは、激しく羞恥と屈辱が込み上がってくるのを感じていましたが、 小夜子さんは、微笑みさえ浮かばせた表情で、ううん、と小さくかぶりを振ると、言ってくれたのでした。 「いいえ、少しも恥じることなど、ないことですわ! あなたは、男らしさをあらわしたというだけです! あなたは、素敵な男性なのです! 私は、そういうあなたが大好きです!」 ぼくは、その言葉に、有頂天になるほどの喜ばしさを感じました。 しかし、喜びは、いつまでも味わっているというわけにはいかないものでした。 老人に施されたぼくの下腹部の処置が意識しないではいられないものとなっていたからでした。 陰茎の根元へ掛けられた麻縄の環からふた筋とされた縄が睾丸を左右から挟むようにして、 それらをまるごと股間へもぐらせているのでした。 ぼくの意思をよそに、陰茎はそうされることで再び硬直を維持されているのでした。 恐らく、普通の男性であれば、かなりの無理があったことのはずです。 しかし、ぼくのように可愛らしい陰茎では、あったものが隠れたという情けなさにしか過ぎなかったのでした。 縄が尻の間から引き絞られることで、陰茎のあった場所には、 代わりに女性のふっくらと盛り上がった小さな丘と似たものがあらわれ、 割れめさえ浮かばせている状態ができたのでした。 尻の間から出された縄には、ご丁寧にも、菊門を刺激し続けるような瘤まで作られていましたが、 ふた筋に背後から割られて、優美な曲線を描く腰付きへ巻き付けられて、縄留めがされていました。 さらに、ふた筋に背後から割られた箇所を結んだ縄が繋がれたことで、 股間の箇所は、立ち尽くした姿勢であっても、女性を見事にあらわして見えたのです。 そして、その繋がれた縄は背筋を伝わって、ほっそりとした首筋を割るようにして正面へ下ろされると、 ふっくらと隆起した乳房のないぼくの胸縄がずれないようにするために、 胸縄の上部と下部へがっちりと結ばれながら、腰縄まで下ろされて締め上げられているのでした。 ああ、それにしても、何という惨めな格好だったことでしょう。 全裸を後ろ手に緊縛されている姿にあるだけでそうなのですから、男性の股縄など、恥辱の極みでしょう。 恐らく、ぼくを見たひとは、すべてがそのように思ったに違いないことです…… しかし、ほかのだれかはいざ知らず、ぼくは……ぼく自身は…… そのような縄掛けをされて、される前は余りに忌まわしく、されているうちは本当におぞましかったことが、 緊縛の終了した縄尻を老人に取られて、部屋の隅に置かれてあった姿見の前まで引き立てられていって、 これ見よがしにみずからの姿態を見つめさせられたとき…… ぼくの何かが変質させられてしまったようになっていたのでした…… ぼくがいま鏡にさらけ出している、生まれたままの全裸を縄で緊縛されている姿態…… それは、老人が名指した<陽間>という言葉に、揶揄なんかではなく、 むしろ、賞賛さえあることではないかと意識させられていたのです…… おまえは、異常なのだ、異常だからだ……だから、そのような異常なことを平気で感じられるのだ…… ぼくもそのように思ってみました……けれど、ぼくの顔立ちや身体付きは、いや、思いにあってさえ、 一般の男性があるようにはないのですから、ぼくは、すでに異常と言えるのでしょう…… ひとの口から、そのようにあからさまに言われたことは、これまでになかったことかもしれませんが、 明らかにそう思っているから取られた言動や行動を感じさせられたことはありました…… ぼくは、異常と決めつけられて、虐めにあってこなかっただけ、幸せであったのかもしれません…… 豊満な女性に憧れることの思いが貧相な男性の現実に押し潰される苦悩はありましたが、 ほかの方だったら、或いは、死にたいと思うほどの苦悩はなかったのです…… しかし、いま、ぼくは、みずからが異常であることを見せつけられているのでした…… そして、そのような異常にあることが、どうして甘美に疼かせる快感を生じさせるものであるか…… ぼくは、その不可思議を柔肌を通して伝わってくる縄の緊縛から感じていたのです…… 生まれたままの全裸にさせられている羞恥、そこへ身動きの不自由をあらわとさせられている屈辱、 さらに、股間へ女性をあらわすように施された特別の縄掛けの恥辱…… どのような見ても、哀切、悲惨、残酷、汚辱、変態、異常としか映らないこと…… そのことが縄の拘束感を持って、舞い上げられるような思いの高ぶりを感じさせているのでした…… 女性のような綺麗な顔立ちと優美な姿態にあったぼくが、 漆黒の靄に包まれて女性のような柔和な小丘と割れめをあらわしていることは、 本当に喜びを感じさせたことだったのです! この世に生まれた以来、今日、初めて、ぼくは…… いや、私は……自分になれたのだという強い思いにあったのでした! そして、女性としてあるのだという思いは、激しく官能を高ぶらせるものであったのです! 「それが、おまえさんを導いてくれる<縛って繋ぐ力による色の道>ということだ! おまえさんがあらわすことを可能とする自分というもののひとつのありようだ! その自分という思いに対して喜びが感じられるなら、そのみずからの思いを思うがままに実現しろ! それが、おまえさんが生きていること、生き続けているということの実感だ!」 老人は、しわがれ声の険しい老いの無表情で、そう言い放ったのでした。 そして、不思議だったのは、私には、もはや、 この老人が不気味でも、忌まわしくも、おぞましくもなく、感じられ始めていたことでした。 私をこのような淫猥、残酷、非情なありさまとさせた鬼の老人であったはずですが、 この方は、私などがまだまだ未熟で知ることのない、 人間のありようの不可思議をご存知なのだろうと感じられたのでした。 導師様…… 小夜子さんが尊敬を込めてそう呼んだ、得体の知れない超絶者であると思え始めていたのです。 その導師様は、私の縄尻を取って引き立てるようにすると、床の間にある柱の方へ連れていきました。 それから、柱を背にして直立した姿勢で立たせると、身動きの取れないように繋いだのでした。 さらに、導師様は、横臥していた小夜子さんを立ち上がらせると、 私の立たせられているすぐ隣にまで引き立ててきて、私と並ばせて同じ姿勢にして繋いだのです。 小夜子さんの柔肌と私の柔肌は密着させられ、相手の上気した温もりが伝わってくるばかりか、 互いの動揺させられている心臓の鼓動さえ、聞こえてくるのではないかと感じられたほどでした。 いや、そればかりか、小夜子さんと私は、ふたりがその気になりさえすれば、 肩越しに唇を重ね合わせることが可能なほどに、間近にさせられているのでした! 愛する女性とこれほどぴったりと寄り添い合うことのできた喜びは、 胸を痛いくらいに高鳴らせるものがありましたが、それにも増して、激しい羞恥もあったのでした。 ふたりの姿がしっかりと見合うことができるように、姿見が運ばれてきて、眼の前へ据えられたのです。  鏡に反映する小夜子さんと私…… 小夜子さんの波打つ艶やかな黒髪に清楚な美しい顔立ち、優しさと慈愛を滲ませているその表情は、 見つめることの羞恥を耐えかねて、大きく綺麗な瞳を横へとそらさせていました。 それは、ほっそりとした首筋、愛らしい乳首をのぞかせて膨らんでいるふたつの美麗な乳房、 優美さは曲線にこそあると思わせる艶麗な腰付き、しなやかに優雅に伸びた両脚、 それらを輝かしいものとさせている乳白色の光沢を帯びた柔肌へ、 後ろ手にさせた縄、胸縄、腰縄、股縄という厳しい縄が掛けられていたからでした。 縄による全裸の緊縛が官能を高ぶらさせていることは、 つんと立ち上がっているのがはっきりと見て取れるほどの乳首のありさま、 股間へ縄を埋没させられて、女の割れめが際立たせられるようにされている箇所には、 女の喜びをあらわす蜜のしずくがきらめいていることで、誰の眼にも明らかなことであったのです。 私も、その姿態を眺めているだけであったなら、妖美、妖艶、艶麗として見つめることができたのでしょう。 しかし、私の端正で綺麗な顔立ち、ほっそりとした首筋、 可愛らしい乳首はあるもののふくらみのない平板な胸、優美さの曲線は負けないくらいの艶麗な腰付き、 しなやかに麗しく伸びた両脚、それらを輝かしいものとさせている雪白の柔肌へ、 後ろ手にさせた縄、胸縄、腰縄、股縄という厳しい縄が掛けられているのでした。 ふっくらとした漆黒の靄の股間へうっすらとのぞかせた割れめが、 その奥へ折り畳まれた陰茎が硬直を増すにつれて如実になっているのでした。 緊縛の拘束感に官能を高ぶらされている状態にあったことで、 肉体へ絡み付いている縄は、まるで淫猥を餌とする貪欲な生き物のように、 肉体の持ち主の欲情、淫情、淫乱、淫心をあからさまとさせていたのです。 何故なら、自然なくらいに伸びやかに、もっともっと官能を高ぶらされたいと望ませていたからです。 それは、もはや、激しい羞恥を感ずる以外に、抑えようのないものであったのです。 しかし、羞恥に抑えられるはずのものでは、到底なかったのでした。 私も、鏡から眼をそらさずにはいられなかったのでした。 身じろぎもせずに、鏡の私たちをじっと眺め続けていたのは、導師様おひとりだけであったのです。 「わしのこの女への<夢の告知>は、これで終わりだ! 後は、おまえさん方がふたりで行い、学び合うことがあるだけだ! わしは、いずれまた、おまえさん方の前へあらわれるだろう! だが、あらわれるわしは、事実であっても、 消え去るわしは、おまえさん方の心象には縄の緊縛としてしか残らない! <縛って繋ぐ力による色の道>が導く<民族の予定調和>は、純潔たる思想であるからだ!」 それから、導師様は、かくしゃくとした様子で、日本間を後にして、 玄関扉へ錠の下りる音を響かせて、去っていったのでした。 日本間に残されたのは……この家にいたのは…… 小夜子さんと私だけでした…… ふたりは、ふたりだけになったことを意識させられると、お互いの存在が際立ったものとなり始め、 ここにいたはずの導師様のことなど、もう、まったく、頭のなかからなくなってしまっているのでした。 私には、小夜子さんが……小夜子さんには、私が……そして、縄の緊縛があるだけでした。 姿見にあらわされているお互いを見つめ合うことなど、尚更、できないことでありました。 全裸を緊縛された柔肌を密着させられて、柱へ繋がれているふたりでしたが、 顔立ちは互いにそむけられ、まなざしは交錯しないように、異なる方へと必死に投げられているのでした。 しかし、ふたりの肉体に施された縄の緊縛は、ふたりがお互いを意識し合う以上に、 みずからのありようというものへ注意を向けさせるものとしてあったのでした。 縄がふたりを結び付けようとしていたのです。 縄の緊縛による拘束感が高ぶらせる官能は、さらなる快感を望ませるものでありました。 果たされないそれは、次第にもどかしいものとして感じられるようになり、気がつかないうちに、 私は、優美な腰付きをうねらせるような身悶えを始めていたのでした。 そして、ああっ、ああっ、とやるせない声音までもらし始めていたのです。 そして、はっ、と気づかされたのでした。 私の官能の身悶えを知って、それに安堵を得たかのように、 小夜子さんの可愛らしい頭が私の撫でた肩へしなだれかかってきたのです。 いや、そればかりではありません。 小夜子さんも、私の態度に付き従うように、悩まし気な身悶えを始めていたのです。 彼女のもらす声音は、私の嬌声など、比べものにならないくらいに切なく甘美な響きがありました。 女性らしさのみなぎったものでありました。 ですから、私も、彼女に負けないくらい、女らしい嬌態をあらわそうと懸命になったのでした。 そして、小夜子さんは、それに煽られるように、さらに、女らしさを発揮していくのでした。 ふたりの女らしさの競合でした。 やがて、緊縛の裸身が火照るまでに上気させられたふたりは、どちらからともなく、 互いの高ぶらされているありさまを鏡にまじまじと見ることをしたのでした。 全裸を縄で緊縛された女がふたり、寄り添い合って、吹き出させた汗で身体全体を光り輝かせ、 それが最後の羞恥とでも言うように、ぴったりと閉じ合わせるようにされた艶めかしい太腿に、 陰茎から滲み出した粘着質のよだれ、ねっとりとした女の蜜をおびただしく滴らせているのでした。 そのお互いのありさまを見つめる端正で綺麗な顔立ち、清楚な美しい顔立ち…… ふたりは、鏡の反映では、もはや、満足の得られないもの感じていたのです。 どちらからともなく、顔立ちを横に向かせて、 お互いの美しい唇を寄せ合おうと突き出すようにさせていったのです。 触れ合わせた小夜子さんの唇の柔らかさは、溶けるくらいの柔和さで、めまいさえ感じさせるものでした。 私は、その甘美さに吸い付いていくのが精一杯でした。 しかし、小夜子さんはお姉さんだったのです、 妹の私など、比べものにならないくらい、女の愛欲を表現することができたのです。 鋭敏に尖らせた甘い舌先が私の唇を押し開いて口中へもぐり込んできました。 そして、うねりくねり、うごめかされました、 唾液のしずくが口の端から流れ落ちるくらいに思いの込められた愛撫でした。 私は、小夜子さんに高ぶらされるままに、緊縛された陰茎を硬直させました。 ついに、甘美な舌と舌とが激しく絡ませ合わされるに及んで、 こらえにこらえていた陰茎は、突き上げられるようにされて、放出を行ってしまったのでした。 けれど、縄で緊縛され股間へ折り畳まれた強要は、弛緩を許さないものとしてあったのでした。 私が昇りつめたことを知ると、小夜子さんも、高ぶらされる官能の突き上げに、 昇りつめたい思いをあらわすように、今度は、私の舌先が挿入されることを求めるのでした。 私は、小夜子さんの口中へもぐり込み、夢中になって愛撫を繰り返しました。 しかし、私の稚拙な愛撫では、小夜子さんは行き着かなかったのでした。 代わりに、彼女は、再び、私を昇りつめさせるほどの熱烈な舌先の愛撫を返してきたのでした。 私は、また、いかされてしまったのでした。 お互いに、はあ、はあ、とやるせない吐息をつきながら、ようやく、唇が離れたとき、私は、詫びていました。 「小夜子さん、ごめんなさい、私が至らないばかりに……」 彼女は、官能に上気した顔立ちに微笑みさえ浮かべて、かぶりを振っていました。 「いいえ……あなたが<陽間>を生きることの喜び…… それに尽くすことのできる、私の喜びです…… 私は、あなたが昇りつめることで、私を学んでいるのです……」 そして、小夜子さんの美しい唇と舌先は、私の唇と舌先をさらに求めてくるのでした。 そのようにして、私は、生まれたままの全裸を縄で緊縛された姿で、 同じく全裸を緊縛された小夜子さんと唇を重ね合って、オーガズムのありようを学んだのでした。 私は、いつまでも、そのような姿態のままであり続けたかった。 しかし、尋常でない体型が永遠に続けられることは、現実にはあり得ないことでした。 それは、導師様が告げられたように、<夢の告知>としてあったことだからです。 夢から醒めれば、現実の生活を生き続けねばならないのです。 しかし、ぼくは、生き続ける道を得たのでした。 <陽間>として生き続ける自覚をもたらしてくれた、小夜子義姉さん! あなたは、ぼくにとっては、なくてはならない女性なのです! ぼくにとって、あのことは、決して忘れられないことなのです!」 熱い思いと共に独り語り終えた健四は、兄の遺影のある祭壇の前まで来ると、 そこへ静かに座り、逝去した者への焼香と合掌を心込めた様子で行うのだった。 それから、義姉の方へ振り返って、告げたのである。 「小夜子義姉さん…… 実は、今日の葬式に、ぼくは<陽間>として、導師様の命を受けて遣わされているのです…… 導師様の命とは、 『葬式は、未亡人が夫と永遠の決別をあらわす厳粛な儀式としてあるものだ、 すなわち、未亡人がひとりの女となったことをお披露目するという厳粛である。 女は、民族の女として、<民族の予定調和>の表象であることを明らかとさせて、 その女を新たな妻として所望する男性へ、お披露目せねばならないということだ。 厳粛な儀式として執り行われることである以上、 いい加減な者がその場に参列する所以はないし、 いい加減な者が女を妻として所望することもあり得ない。 <民族の予定調和>の表象としての女性を真に求める者だけがあるということだ。 女にそのようにせよ、と伝えよ』 ということです」 告げられた小夜子は、大きく綺麗な瞳を見開いたまま、 蒼ざめた真剣な表情を浮かばせて、相手を見やっていた。 「……導師様がそのようにおっしゃられるのですか…… それが<縛って繋ぐ力による色の道>を歩む私の成すべきことであるとされるならば、 私には、従うことでしかありません…… 私を引き立てて頂けるのは、あなたさま、<陽間>様でいらっしゃるのですか。 そうであれば、小夜子にとって、このような幸せはありません……」 そして、その美しい顔立ちをもたげて、まじまじと相手を見つめるのだった。 健四もまた、端正で綺麗な顔立ちへ、引きつっているくらいの真剣な表情を浮かべて、答えていた。 「もちろんです……ぼくにとって、何よりも光栄な役目です! では……小夜子さん、身に着けているものをすべて取り去ってください……」 男は、携えて来たトランクを開くと、なかから麻縄の束をごっそりと取り出した。 女は、立ち上がって背を向けると、喪服の帯締めへ、ほっそりとした白い指を掛けるのだった。 それから、帯締め、帯揚げを抜き取り、帯を取り外し、着物姿になったところで、伊達巻や腰紐を抜いていくと、 着物の裾前は自然と割れて、黒の艶めかしさに対して、 そこはかとない白の純潔の色香を漂わせた長襦袢があらわとなった。 長襦袢の腰紐を解き、肌襦袢の紐を解き、躊躇も見せずに、撫でた柔和な両肩からそっとすべり落させた。 あらわれたふたつのふっくらと盛り上がった乳房の美しさは、その先端へのぞかせた乳首の愛らしさと共に、 あたりをも明るくさせるくらいに光沢を帯びた乳白色の柔肌を眼に染み入るようなものとさせていた。 残る下半身を覆う湯文字と足袋は、かがみ込んで立膝を突きながら、 優美な腰付きから、小さな形のよい足から、剥ぎ取られていって、 女は生まれたままの全裸の姿となったのだった。 じっと眺めていた男も、その見事な脱ぎっぷりには感心させられていたが、 女がほっそりとした両手首をみずから背中で重ね合わせる姿勢を取ったことは、 思いの生真面目さをあらわすように健気にさえ映ることだった。 男は、その重ね合わせた華奢な両手首を縛り、縄尻を身体の前の方へ持っていって、 綺麗な乳房の上部へ二重にまわして背後で縄留めすると、さらに、もう一本の縄を背中から、 今度は、乳房の下部へ二重にまわして、双方の腋の下から緩みの起らないように締め上げていった。 さらに、背中へ繋がれた新たな縄がほっそりとした首筋を左右へ割って正面へと持ってこられ、 上下の胸縄へ絡められることで、ふっくらとした綺麗な乳房は突き出すような具合にされて、 下ろされた縄は優美な腰付きへ巻き付けられて、女らしいくびれを際立たせるように締められるのだった。 その腰縄には、臍のあたりで結ばれた縄が縦へ下ろされ、 艶めかしい漆黒の靄に隠れる女の割れめへもぐり込まされていった。 股間を通されて優美な尻の間から這い上がった縄は、しっかりと割れめへ埋没するように整えられると、 手首を縛った縄へ留められて、表象としての全裸の女体緊縛姿が作り出されたのだった。 男にとっては、今日、初めて縄を掛けた女性であったが、 縄掛けに反応していく様子が経験豊かな女性であるとは思えない初々しさを漂わせることに、 強く感動させられるのであった、できれば、この女性と一生を添い遂げたいと思うことではあったが、 <陽間>は独身を身上としていることであったのだ。 男は、羞恥に俯いてまなざしを落としている女の縄尻を取ると、 ちょうど祭壇の隣になる床の間の柱まで引き立てていって、そこへ直立した正面の姿勢で繋いだ。 それから、男は、みずからも、身に着けていた黒の礼服から始めて、すべてを脱ぎ去り全裸の姿となった。 そして、可愛らしいほどの陰茎の根元へ麻縄の環を掛けると、 そこからふた筋とした縄を睾丸を左右から挟むようにして、それらをまるごと股間へともぐらせていった。 尻の間から這い出させた縄が引き絞られ、陰茎のあった箇所へ女性のふっくらと盛り上がる小丘が作り出され、 ふた筋へ割られた縄は、女性らしい優美な曲線を描く腰付きへ巻き付けられて、縄留めが終了した。 女の割れめさえのぞかせる、<陽間>の姿態があらわとされたのだった。 <陽間>は、脱ぎ散らかされた男女の衣類をきれいに片付けて、床の間の柱まで行くと、 生まれたままの全裸を縄で緊縛された女の縄尻を掴んで、直立した姿勢でその隣へ並ぶのだった。 葬式の最初の弔問者があらわれるまでに充分の時間はあったが、 ふたりの緊縛姿の男女は、厳粛を示すように、身じろぎもせずに立ち尽くしているのだった。 しかし、全裸を縄掛けされている境遇は、おのずと官能を高ぶらせるものであったから、 ふたりがそれをこらえ尽くすということに、 <おごそかで、心が引き締まるさま、きびしくゆるがせにできないさま>、 という<厳粛>の意義が明らかにされていることだったのである。 従って、この<厳粛>は、当然、弔問者にも求められることであって、 <厳粛>に同意を持たない者の参加は許されないことであったのだ。 <縛って繋ぐ力による色の道>が導く<民族の予定調和>が単なる<猥褻>ではなく、 <正統性ある猥褻論理思想>であると言っている理由は、こうした<厳粛>が不可欠とされることにあった。 縄で緊縛された生まれたままの全裸の女性が公然とされるだけのことであれば、 それは、雑誌でも、映画でも、インターネットでも、日常茶飯事に見ることができるものである。 そこには、芸術性の云々は取り沙汰されても、<厳粛>は爪の垢ほども存在しない。 公衆の面前へ全裸緊縛女性があらわれたとなれば、公然猥褻物陳列という刑法上の罪に問われるか、 よくて、好奇と嘲笑と揶揄と非難の対象となるに過ぎないことである。 従って、<正統性ある猥褻論理思想>は、そこへ参加する者の<厳粛>の意思に依存することだった。 最初にあらわれた弔問者は、健一の双子の弟の健二であった。 <民族の予定調和>の<信奉者>幹部であった健二は、 <陽間>が表象の女性を引き立てているありさまを見せられて、未亡人のお披露目を理解した。 小夜子を所望する第一人者は自分のほかにはないと自負していたから、 思いは、喜びと幸せに満ちた彼女との新婚生活へと舞い上がっていた。 次にあらわれたのは、健一の弟である健四の双子の兄の健三だった。 <信奉者>である健三も、お披露目を理解したから<厳粛>への同意はできたが、 二十歳の年齢でまだ結婚は考えていなかった、 ただ、熱烈な憧憬を抱く義姉の美しい全裸の緊縛姿に見惚れているばかりであった。 それから、彼らの両親がやって来たが、将来に期待をかけた溺愛する長男の遺影と並んで、 その嫁が生まれたままの全裸を縄で緊縛されて晒しものとなっているばかりか、 末の息子まで全裸であって、しかも、異様な股間をあらわとさせているありさまに、 父親、母親、共々、激しい驚愕と狼狽の態度を示したが、その場の水を打ったような<厳粛>に、 愛する息子の葬式をぶち壊しにする不同意を示すようなことはしなかった。 そして、身内の最後である、健一の三歳年下の妹である双子の姉妹があらわれた。 名前を、美恵、恵美と言ったが、 どちらを序列の先と判断するかは、名前では分かりにくいところであったが、 美恵が姉で、恵美が妹である、と覚えておく必要があることかどうかは、 今後の彼女たちとの交際関係に依っていることであった。 ふたりは、小夜子と同い年であったわけであるが、 結婚の当初から、意地の悪い小姑ぶりを発揮している双子姉妹であった。 この場合も、小夜子の全裸緊縛姿を見た瞬間、異口同音に叫んだ言葉はこうだった。 「何と恥さらしな真似をしているの! ふしだらでいい加減な嫁だと思っていたけれど、まさか、こんなとはね! このような醜態を晒すなんて、一族の恥辱を世間に訴えているようなものだわ! よくもまあ、皆、平然とした顔で厳粛を装っていられるわね! こんな荒唐無稽で、猥褻で、非人道的な葬式なんか、参加できるわけがないじゃない! 常識が疑われるわよ! 帰らせてもらうわ!」 そのように怒声を吐き捨てて、帰ってしまったのだった。 <縛って繋ぐ力による色の道>が導く<民族の予定調和>をまるで知らない者にしてみれば、 取って当然の態度であったと言えることだろう。 だが、ほかの親族は、わがまま娘の相変わらずの身勝手としか見なさなかった。 葬式の<厳粛>は、それで損なわれるものではなかったからだった。 それから、訪れた弔問客は、式場に漂う<厳粛>と異様な姿の男女を同意した者は残り、 常識の埒外だと不同意を感じた者は焼香を済ませるとすぐさま退去していった、という結果を生んだ。 この場合、有名な女優が小夜子の代わりにでもあれば、状況はまた違った展開を生んだのかもしれないが、 ひとつの民族思想がその知名度を上げるには、相応の時間もまた必要であるという証明であった。 結局は、出棺に際して式場に居残った者は、弔問客の百名に対して、わずかに五名だった。 つまり、五パーセントということであって、五パーセントのアウトサイダーの存在と呼ばれていることであり、 この一般性の概念に対する特殊性の概念の認識許容数値は、平均的な結果を示したということである。 その五名に対して、親族を代表して、 <陽間>の健四が挨拶を述べたのだった。 「本日はご多忙のなか、兄、健一の葬儀にご参列を頂き、誠にありがとうございました。 兄もこれで黄泉の国へと旅立って行くわけでありますが、 残された妻は、尚、現実を生き続けていかなければなりません。 ご覧の通り、未亡人、小夜子は、<民族の予定調和>の表象である女性です。 表象の女性であるからこそ、このような羞恥の姿をさらけ出すことをしている次第です。 その羞恥は何のためにあるかと言えば、 いずれ訪れる<民族の予定調和>実現のためです、そのために、彼女は、 <縛って繋ぐ力による色の道>をさらに歩み続けることをしなければならないのです。 このことをご理解、ご納得頂ける方、この美しい女性を是非にも妻にとご所望される方がお出でであれば、 どうか、美しき良き妻を持っていた兄の決別と旅立ちのはなむけとして、 この場で申し出て頂きたい所存です。 お願い申し上げます……」 生まれたままの全裸を後ろ手に縛られ、胸縄、腰縄、首縄、股縄を施された緊縛の女を引き立てて、 <陽間>は、女性の姿態と股間をあらわとさせた男性として、深々と会釈をするのだった。 健二が、みずからの出番はここぞ、と名乗りを上げようと前へ出ようとしたときだった。 それよりも早く、ひとりの中年の男性が小夜子の前へ立っていた。 「私は、大江という者です、大学で日本文学を教えています。 健一君はかつての私の生徒でした。 <民族の予定調和>というのは初めて聞くことですが、 こちらの女性の放つそこはかとない美しさから判断すれば、深く研究にあたえする興味ある事柄と思えます。 私は、武士道を信条としています、茶もたしなめば、花も生けるし、書を描くこともします。 日本の純然たる民族思想である武士道とその興味深い<民族の予定調和>が結ばることになれば、 これまでにない、新しい日本の自意識が生まれることは間違いないことだと思えます。 是非とも、美しい小夜子さんを私の妻に頂きたい、お願い致します」 大江と名乗る男性は、小夜子へ向かって深々と頭を下げるのだった。 未亡人は、全裸を縄で緊縛され、高ぶらされていた官能から上気させられた顔立ちをさらに赤らめて、 はい、と優しい声音で述べて、承諾を示したのであった。 こうして、小夜子は、夫の葬式を厳粛なうちに無事済ませると、優れた国文学者の妻となり、 その後の<縛って繋ぐ力による色の道>を迷うことなく歩み続けたのであった。 武士道を信条とする新しい夫は、 <民族の予定調和>に対する理解と納得を<信奉者>である者以上に示した。 初夜の晩から、小夜子は、生まれたままの全裸を縄で縛り上げられ、 柱に繋がれてしなやかな両脚を広げさせられ、艶めかしい女の花びらと深淵を深く研究された。 学者にとっては、得体の知れない思想や論理よりも、実証こそ第一の叡智であるという認識があったから、 女の清廉な割れめは、学者の探求心にあふれた指先で、穴においては上から下まで隈なく掘り下げられ、 突起においてはしこるほどに掘り起こされたが、<民族の予定調和>の表象があらわす実証は、 学究の指先に見事な反応を示して、黄金水ばかりでなく、女性でなければ吹き上げられない潮まで噴出させて、 甘美で悩ましいよがり声を上げながら、挿入されるあらゆる事物に吸引と収縮で痙攣したのであった。 女の顔立ちや姿態の美しさばかりでなく、縄で緊縛された全裸でオーガズムへ到達する妖美は、 <民族の予定調和>は決してまやかしではないと思わせるほど、学者を感動させたのであった。 そこで、学者は、みずからの叡智を女に教え込むという段階へ昇級させた。 小夜子は、武士道の奥義を伝授すると申し渡されて、緊縛された全裸姿のまま道場に立たされた。 逃れることのできないように天井からの縄に繋がれて、股間へ竹刀を差し入れられた、それから、 女としての鋭敏さを鍛える稽古として、竹刀を割れめへ突き上げられて、官能を昇りつめるまで繰り返された。 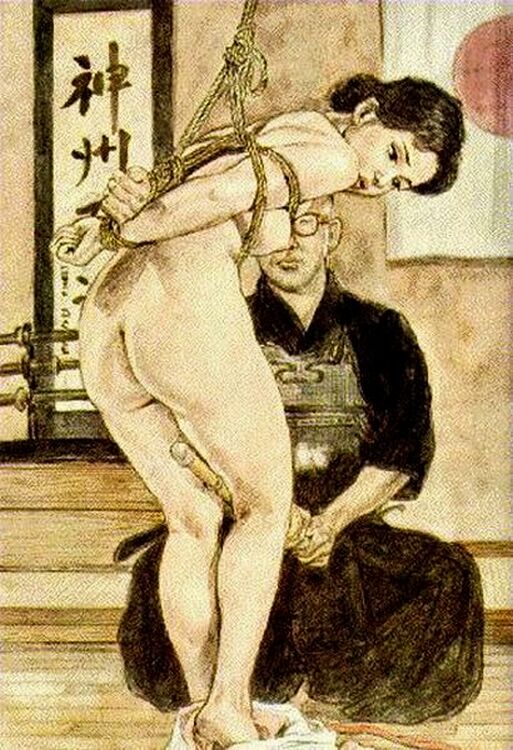 さらに、女としての教養を高めるためとして、茶室にて、全裸を緊縛された姿態で、 わびさびという茶のたしなみを女の割れめから学ばされたり、 緊縛という身動きの取れない姿態で、風流、華麗、優雅の生花のたしなみを女の花園で学ばされたり、 流麗、雄渾、幽玄という書のたしなみを緊縛の裸身の三つの穴とひとつの突起へ描かれることで、 日本女性として発揮される美を修練させられたりしたのだった。  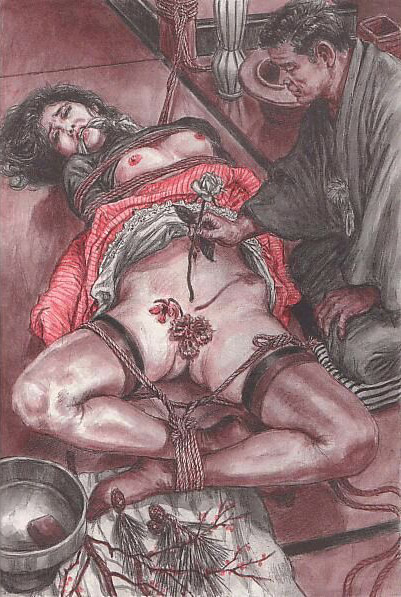  しかし、小夜子は、民族の女性であり、<民族の予定調和>の表象であったから、 夫の求めるどのような淫猥な要求にも見事に応えて、ますます輝ける<色の道>を歩んでいったのであった。 少なくとも、その夫が腹上死で急死するまでは、幸せに暮らすことのできた日々であったのだ。 再び迎えなければならない、葬式の厳粛な哀切のときまでは。 …………… この成行きに対して、権田孫兵衛老人はこのように批判した。 <民族の予定調和>の表象として、女性が幸せになるのは、りんごが木から落ちるほど必然性のあることだ。 同じように、人間の死も、生が必然的であるのと同程度に必然的であるが、 新しい夫の急死があらわされる終わり方は不自然であるとしか言いようがない、とされたのである。 激しく官能を高ぶらされていたとしても、小夜子が余りにも簡単に求婚を承諾したことは、 同程度に、新しい夫の腹上死が急死の可能性として自然であるとしたことに依るが、 答えは、次なる想像力の展開へ向かう以外にないことであろう。 |
☆NEXT ☆BACK ☆権田孫兵衛老人のアンダーグラウンド タイトル・ページ |